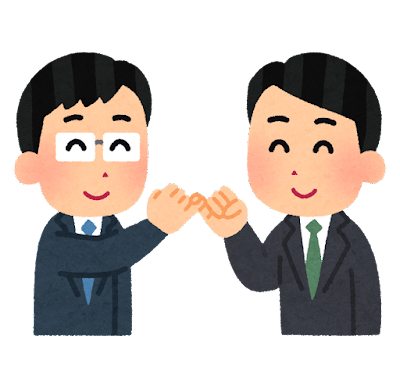「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」を読んでないくせに、ぶったタイトルですみません。
「トランジスタラジオ」と聞いてみなさんは何を思い出しますか?
今回は往年の名曲「トランジスタラジオ(RCサクセション)」のお話ではなく
9年前に78歳で亡くなった私の母の話です
といっても、皆さんからよく聞くやさしい母の思い出話、というのとも少し違うかな。
なんせ庄内藩上士の家系の7人兄弟の末娘として生まれ育った母。
プライドが高く、特に長男の私に対するしつけにはなかなか厳しいものがありました。
たぶん生まれてから一度もほめられた記憶がないほどです。
まあこちらも、世間様に自慢できるような、賢い元気な男の子ではなかったので、それも致し方のないことですね。
さて、本題。
この話を聞いたのは昭和50年代、私も成人してようやく一人前だと認められ、母が老境に差し掛かった頃。
彼女が中学1年の頃の思い出話をしてくれました
母は昭和11年生まれでしたので戦後まもない昭和20年代前半のお話。
科学の先生が授業中にポツリと言ったそうです。
「そのうちラジオは手帳くらいの大きさになって、シャツのポケットに入るようになるぞ」
その瞬間・・・教室は大爆笑の渦に包まれました。
なぜなら、「こんなに大きくて」と母は手で小さな仏壇くらいのサイズを示しました。
その頃のラジオは茶だんすの上に安置して、家族みんなで聞くものだったからです。
(朝ドラの「カムカムエブリバディ」やなんかを思い出してみてください。)
「でもね〜 それからすぐラジオは真空管からトランジスタになって、10年かそこらで、ほんとにポケットに入るようになっちゃったのよ」
と、母は話を続け
「だから、今はまさかとか絶対ムリってことでも、いつかはそうなっちゃうって思ったほうが良いよ」
と、締めくくりました。
歴史を紐解くと、トランジスタラジオはベル研究所によって1948年(昭和23年)にプロトタイプが作られ、ソニーの量産型第一号が発表されたのが1955年(昭和30年)、なので史実と母の話と符合します。
科学の先生はどこかで、ベル研究所のトランジスタラジオの情報を読んでいたのかもしれませんね。
そう考えてみれば、蒸気機関車や飛行機などが発明される頃、民衆はそのアイディアを聞いて、母の同級生のように大爆笑していたのではないでしょうか?
もしかすると、もっと前、馬車とか弓矢とか、さらにある人類が火を起こそうとしたときにも、それが成功して凄まじい威力を発揮するまで、周りは爆笑し続けていたかもしれません。
自分の身を振り返ってみても、多少情報通信の知識があったので、インターネットについては「これはえらいことになるぞ」と、小さな会社で整備を進めましたが、スマホが出た時はすぐにその意味をわかることが出来ませんでした。
「そんなにスティーブが言うのなら(生意気)」と、少し遅れてiPhone3Gを入手してみて、初めてその革新性を理解できたという次第。
量子コンピュータの話も2000年頃には雑学ネタとして簡単な原理は知ってましたが、「ワープ」と同じようなSFチックなイメージしか持てず、こんなに早く実用レベルに近づくとは夢にも思いませんでした。
さて、最近なんと言っても話題なのが「ChatGPT」に代表される「生成AI」です。
「生成AI」は与えられた入力データから新しいデータを生成することができる人工知能技術のこと。
具体的には「ChatGPT」のように質問に対して答えてくれたり、注文に応じて文章を作成してくれたり、さらには画像や動画、音楽まで作ってしまうことができるとか・・
「人間の創造性を増す素晴らしい技術」という高評価から「人間の尊厳を侵すいけないもの」というネガティブ評価、さらには「人間から仕事を奪い、支配者になってしまうのでは」という恐ろしい予測。
逆に、「いやいやいや、過去のデータから生成されたものになんの意味があるの?」という超disりまくり評価まで・・・
さまざまな評価・予測の中で「いったいどこまで進むのか?」戸惑うばかりの私ですが、じつはあんがい楽観的にこの騒ぎをとらえています。
亡き母の言う通り「今はまさかとか絶対ムリってことでも、いつかはそうなっちゃう。」
そう考えれば、生成AIはいつか「人間から仕事を奪い、支配者になっちゃう」のかもしれません。
しかし人間はとっくのとうに、自分たちが発明した文字やお金、さらにラジオや自動車にまで支配されています。
文字の記録のせいで約束も破れず、お金のために必要以上に働き、ラジオで誰かが言ったことに踊らされ、自動車にひかれたりしています。
でも、文字がなければ約束を忘れ、お金がなければ他人がしてくれたすばらしいサービスに報いることができず、ラジオがなければビートたけしはただの漫才師で終わり、自動車がなければ移動の自由は貴族だけのものだったでしょう。
生成AIに支配された私達は、次に一体何を手に入れるのでしょうね。